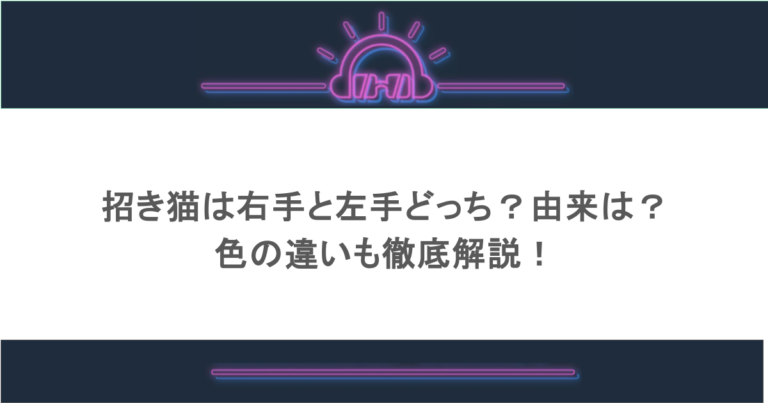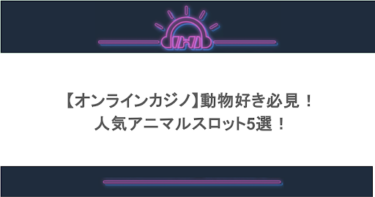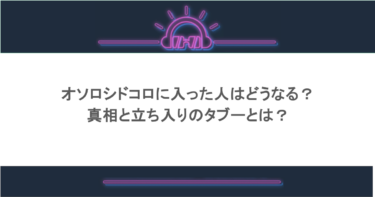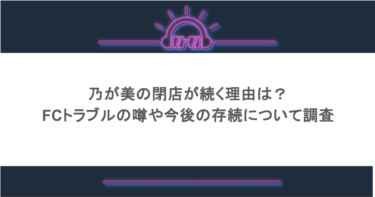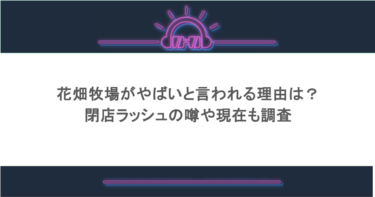招き猫の手の上げ方には、右手と左手、そして両手上げの3種類がありそれぞれ意味が異なります。さらに招き猫の由来や色の違いもそれぞれ意味が異なる他、置く場所にもこだわりがあるというのを知っているでしょうか。今回は福を招くといわれている招き猫の手に関する意味について様々な要素から紹介していきたいと思います。
招き猫は右手と左手どっち?
招き猫は古くから日本で幸運を呼び込む象徴として親しまれてきた縁起物です。その姿は片手を上げた猫がちょこんと座っているのが一般的ですが、実は招き猫にはバリエーションが様々あり、手だけでも異なる意味を持っています。
右手を上げた猫は「金運を招く」といわれ、左手を上げた猫は「人やお客を招く」という意味があります。そのため意味によって置く招き猫の手が異なるということです。
Title 招き猫
右手 : 金運や幸運を招く
左手 : 人やお客を招く#招き猫 #招き猫の絵#絵描きさんと繋がりたい#絵描きさんフォロバ100#色々な人と繋がりたい pic.twitter.com/UUrnRJZseJ— Reiko.Onodera 小野寺玲子 (@OnoderaR2486) January 7, 2025
両手を上げた招き猫
片方の手を上げている招き猫はそれぞれ意味が異なりますが、両手を上げている招き猫も存在します。これは「金運」と「人を招く」両方の願いを込めたものです。
しかし一部の人には「欲張りすぎて逆に良くない運を招く」ともいわれているため用途に応じて選ぶ方を工夫することが重要となります。手の高さによっても遠くからの運を招くものや近くからの運を招くという意味もあるようです。
『お金も人のご縁も笑顔からやってきます』
○リプライ&イイネで参加します。
○両手を上げている招き猫は、
ご縁と富の両方を呼び込みます。@sweetkialla @55ALt5kdNdMD1Gl pic.twitter.com/cCz2xLc4Dq— 開運ゴールドルーシャ| お金の神様|フォローで、あなた様の金運を大向上祈願 (@Lucha_kansya) November 7, 2023
招き猫の由来
招き猫の起源には諸説あり確定した説はありませんが、代表的なものとして江戸時代初期江戸で活躍していた武士が鷹狩りの途中で、豪徳寺の前を通りかかり寺の猫が手招きする姿を見て寺に立ち寄ったとされています。その後寺の住職と話している間に雷雨が降り結果的に命を救われたという豪徳寺説があります。
一方では貧しい老女が夢のお告げに従って猫の姿をした土偶を作ったところ、それが売れて生活が豊かになったという浅草寺説もあります。
招き猫が持っているもの
招き猫といえば小判を持っているイメージですが、初期の招き猫には小判はなく首輪に鈴をぶら下げている姿がほとんどでした。小判に縁起のよいものが描かれ願いがダイレクトに反映されています。現在では手に持っているのは小判だけでなく鯛やダルマ、熊手や打出の小槌などの様々な縁起物を持った招き猫があります。願いの数だけバリエーションがあるように変化していきました。
色による招き猫の意味
招き猫には手の他に色やデザインの違いによって様々な意味が込められています。例えば白は「純粋さ」「幸運」、黒は「魔除け」、赤は「健康」「病気予防」、金は「金運上昇」、青は「学業成就」、ピンクは「恋愛運」を象徴しています。
これらの招き猫は伝統的なスタイルに加えてデザイン性を重視したモダンなものが多く、若者にはシンプルで洗練されたデザインやカラフルな個性的なものが人気を集めています。
古くから一般的な招き猫
招き猫の古くから一般的なデザインは、真っ白なものや白地に三毛のぶち模様のものが多く見られます。
汚れのない白は「開運招福」を意味し、万事に福をもたらすといわれています。黒の招き猫は西洋では不吉だとされていますが、日本では夜目が聞くことや強い霊力を持つと考えられた事から「福猫」として扱われていました。赤い招き猫は昔から疱瘡神が忌み嫌う色といわれていたことから「病除け」「健康長寿」の御利益があるといわれていました。
西洋ではいまだに「黒猫は不吉」というのが根深いそうで保護施設では黒猫が余っているそう。
日本の黒の招き猫は厄除け、
右手をあげているのは金運を呼び込む縁起物なので、
西洋で黒の招き猫を流行らせられないものか、、、🤔 pic.twitter.com/tVzonOQ7kz— しっぽな・多頭飼育崩壊レスキュー (@sssiiipppooo) December 23, 2024
まとめ
今回の記事で、招き猫は右手と左手のそれぞれに意味があることや、色やデザインが初期から変化を遂げていることについて紹介していきました。
初期の頃は小さな幸せを願って作られていましたが、今ではそれぞれの願いに合わせたデザインで作られていることがわかります。また色による意味も込められているので、誰かの願いを叶えてほしいなどの時には意味を調べて送ることもできると思います。