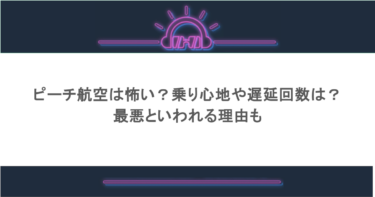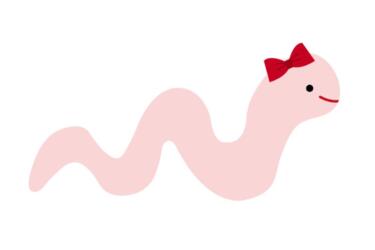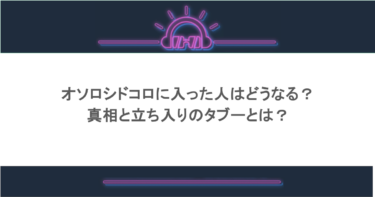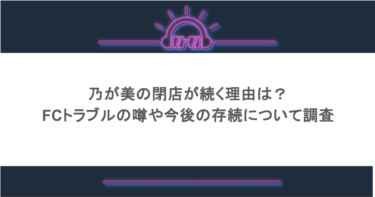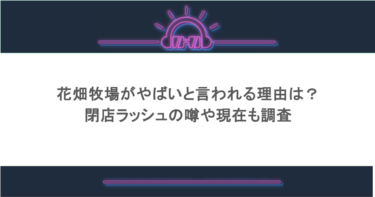今年も節分の日が近づいてきましたね。節分といえば恵方巻ですが、恵方巻きを食べる時に向く方角は誰が決めるのか知っていますか。今回は恵方巻きの方角や具材の意味などについて調査しました。
恵方巻きの方角を決めるのは歳徳神
恵方巻きの方角を決めているのは歳徳神という神様です。「としとくじん」及び「とんどさん」と呼ばれ、天文学や暦の知識を駆使して日時や方角、人事全般の吉凶を占う陰陽道における、その年の福徳を司る神が歳徳神なのですね。その姿は、王妃のような美しい姫神として伝わっています。
恵方巻の方角、つまり恵方は歳徳神のいる方位のことを言います。つまり恵方巻は歳徳神のいる方角に向かって食しているということになりますね。歳徳神のいる方角は年によって変わるため、恵方も毎年変わるというわけです。
恵方の決まり方は?
恵方は歳徳神が決める、といっても、現実問題歳徳神の存在は誰も認知出来ず、歳徳神がどこにいるのかは誰にも分かりません。実は恵方には具体的な決まり方があり、西暦の一の位の数によって決まっているのです。一の位が5である2025年の恵方は方位角で255度ですよ。
恵方は「南南東」「北北西」など、方角三文字で言われることが多いですよね。ですが16方位では「南南東やや南」、32方位では「南微東やや東」など、より細かく決まっているようですね。
実は南南東の年が多い!
皆さんはこれまで生きていて、なんとなく「この恵方の年多いな」と感じたことはありませんか?西暦の一の位が4・9の年は東北東、0・5の年は西南西、2・7の年は北北西と、それぞれ一つの方角に対応する数字は二つなのですが、南南東に対応する一の位の数字は1・3・6・8の四つあるのです。実は南南東になる年が多いということですね。
恵方はなぜ4方位に振り分けられる?
恵方は正確には西暦の一の位というよりも十干によって決まっているのです(干支の十干十二支の十干、十個しかないので自然と一の位と対応するというわけです)。十干は木、火、土、金、水の五行をそれぞれ陽と陰に分けたものであり、木と火と金と水にはそれぞれ方角が設定されています。しかし土には方角が定められていないので、土の年には代わりに火の方角が当てはめられているのですね。
恵方巻きの具材には意味がある?
実は恵方巻の具材にも正しい形というのがあるようです!恵方巻として食べる太巻きには七福神に因んだ七種類の具材を使うとされており、「福を巻き込む」という意味で恵方巻きを食べるのですね。また、太巻きを逃げた鬼が忘れていった金棒に見立てて、鬼退治と捉える説もあるようです。
具材の七種は特に決まっていないものの、主に以下の七種が代表例となっているようです。
- 高野豆腐
- かんぴょう
- キュウリ(レタス・かいわれ)
- 伊達巻(だし巻・厚焼き玉子)
- ウナギ(アナゴ)
- 桜でんぶ(おぼろ)
- シイタケ煮
なんだか、全体的に渋いですね。
具材に何を使うかよりも七種の具材を使うことが大事
ただ、調べてみたところ、上の七種の具材それぞれに意味があるという訳ではないようです。あくまで七福神になぞらえた七種の具材、という形が大事なようです。様々な具材を一緒に巻いて食べるということで、具材同士の相性などで上の七種がメジャーとなったのかもしれませんね。
近年は恵方巻が販売される店も多くなり、マグロやサーモンなどの人気の寿司ネタを使った恵方巻きも多く見られるようになりました。七種にこだわらない人も多く、単に「恵方を向いて巻き寿司を食べる日」と認識している人もいるようですね。
最後に
今回は恵方巻きの方角や具材の意味について紹介しました。ちなみに恵方については、例外的に通常とは異なる方角になる「飛坎年」というものがあり、これは3600年周期で訪れるそうです。西暦2028年はまさにこの飛坎年であり、この年の恵方は「北」、真北なのだとか!